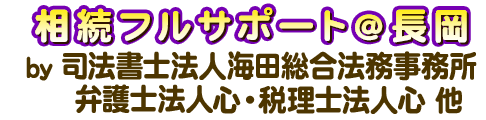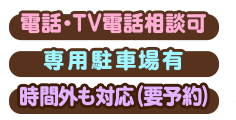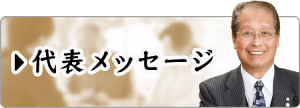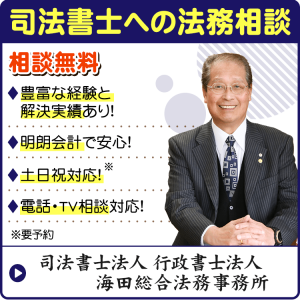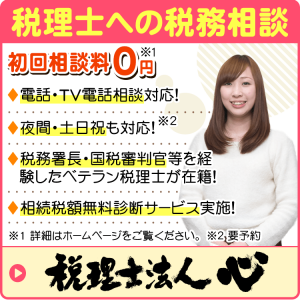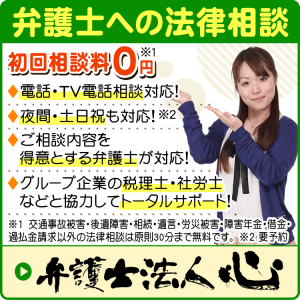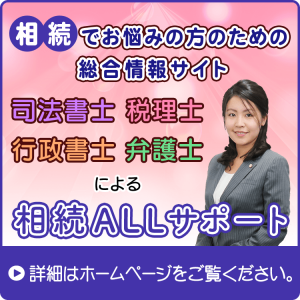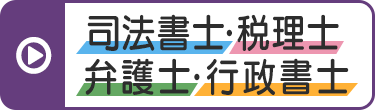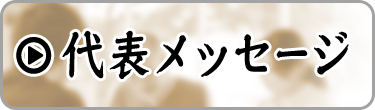法定相続情報一覧図の使い方や取得の流れ
1 法定相続情報一覧図の意味
法定相続情報一覧図とは、被相続人とその相続人を図式化して記載したものをいいます。
被相続人の最後の住所地、被相続人の出生日と死亡日、相続人の住所地、出生日などを記載し、作成日や作成者を記載したうえで図式化し、戸籍謄本・除籍謄本と一緒に登記所に提出して作成します。
登記官が、一覧図と戸籍謄本・除籍謄本との内容が合致していることが確認できれば、その一覧図に登記官の認証文を付けて、写しを無料で発行してくれます。
2 法定相続情報一覧図の使い方とメリット
登記官の認証文のついた法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等の代わりになります。
相続手続には、預貯金通帳の解約・払戻し、相続登記手続、被相続人の証券口座の解約、相続税申告手続など、様々な手続がありますが、いずれにおいても被相続人が生まれてから亡くなるまでの間の戸籍謄本・除籍謄本等の資料が必要となります。
ただ、法定相続情報一覧図があれば、これらの戸籍謄本・除籍謄本は不要となりますので、手続を簡略化することができるメリットがあります。
3 取得の流れ
被相続人が生まれてから亡くなるまでの間の戸籍謄本・除籍謄本をすべて集める必要があります。
被相続人と戸籍謄本の記載にある相続人を一覧にした図を作成する必要があります。
サンプルは法務局のホームページも記載があります。
申出書に必要事項を記入したうえで、必要書類と作成した法定相続情報一覧図を揃えたうえで登記所に提出をします。
提出する先の登記所は、どこでもよいわけではなく、被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかの登記所になります。
直接持参することもできますし、郵送で手続を行うこともできます。
ご自身で作成することが難しい方は、代理人に依頼することもできます。
代理人となることのできる人は、親族の他、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、海事代理士、行政書士などが可能です。